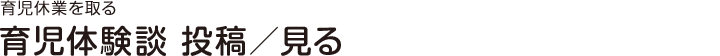見る
育児体験談を『見る』
入力欄に検索したいキーワードを入れて下の検索ボタンを押して下さい。
また、年代やエリア、お子様の人数などを選んで検索することもできます。
全 688件中、101件目 ~ 110件目を表示 (11/69ページ)
【写真】梅雨が明けたら布おむつに切り替えるため、ドビー織の輪おむつを仕立て中
生後1ヶ月半から6ヶ月の育児休業を取得し、3ヶ月が経過しました。
息子の日々の成長を間近に見て、妻と分かち合えることに喜びを感じています。
食事の準備中に母乳タイムになったとき、妻のエプロンをもらって台所に立てるほど家事が上達しました。育児も半日程度なら安心して外出できると妻からお墨付きです。
先日、息子が風邪をひいてしまい寝たまま上を向いて嘔吐。1時間前に飲んだ母乳を全部出してしまいました。側にいたのですぐに介抱したのですが、窒息をしていたらと思うとぞっとします。育児休業をとっていて本当に良かったと感じました。今は風邪も完治し減ってしまった体重も戻りつつあり一安心です。
残り3ヶ月も悔いのないよう育児休業を満喫し、休業後も今の気持ちを忘れずに育児、家事に向き合っていきたいと思います。

ようすけ
30代男性 子供1人
私は、妻と長男の3人家族です。いまでは、子供が大好きですが、実を言うと、大がつくほどの子供嫌いでした。しかし、長男の誕生をきっかけに、その考え方も180度変わりました。できる限り子供との時間を大切に生きていきたいと考えています。
それは、コミュニケーションをできる限り、つくりたいとの想いがあるからです。その理由は、私は女で一つで育ててもらいましたので、母親は仕事に家事にと両立しければならない状況でしたので、私との時間もコミュニケーションを取ることも少なかったように思います。そういった実体験から、子供とのコミュニケーションが大事だと考えており、子供との時間を多く取っている次第です。
とはいうものの、おむつ替えや寝かしつけることなど、正直、大変なことが多いですが、ふと見せる子供の笑顔、家内の笑顔を見るとそのようなことも一瞬で吹き飛んでしまいます。
育児は楽しいということをどんどん広めていくお手伝いができればと思い、登録させていただくことを決意いたしました。

佐山 亮光
30代男性 子供1人
今日は午後会社を休んで子供のお迎えにいきます。
妻には夜友人と会食にでもどうぞ~と。
お風呂と食事、洗濯までできるパパを演じます!

ともき
40代男性 子供1人
私は妻一人、子一人の新米パパです。
子供は今月で6ヶ月、初めての男の子になります。
生まれる前から育メンとして妻を支える自信があり(なぜか)、
準備万端で子の誕生を待ち望んでいました。
ただ、生まれてからの育児は想像を絶するものでした。
最初の方はおむつやミルクをあげつづけ、
「なぁんだ、簡単じゃん」と考えていました。
ところが…
ミルク、おむつても泣き止まない。
寝返りをうちだし布団から転げる、うつ伏せになる。
ヒザにのせるとのけ反って落ちそうになる。
手当たり次第に口に入れる。
etc…
子育てが日々絶え間なく続くこと。
奥さん独りでは非常に辛く苦しいこと。
なにより【命への責任】に対する重圧が、
仕事への責任の何百倍もあること。
私は身をもって知りました。
子供は二人ないし三人を予定しています。
子供達がすくすく成長する場を形成するのはもちろん、
妻が日々のびのびと子育てや仕事(やりたくなったら)に、
集中できる環境を私は創っていきたいと考えています。

みずゆう
20代男性 子供1人
育児休暇の申請をしてから思ったこと。
男性の育児休暇取得の第一関門は身内ですね。親の世代の理解を得るのは大変。
妻も、そんなに家にいられても困る、と(笑)
仕事と家事の両立から、家事だけに専念することができるようになることで、
「家事を手伝う」から「家事を担う」になるべく半年間で育児休職の経験を積み、3児のパパをやってみるつもりです。
時代の変化に合わせて、がんばってみます。

はるきパパ
30代男性 子供3人
お腹にいる時から、毎日話しかけて、歌を唄いました。毎回の検診も同席してお医者様からアドバイスをいてだきました。これからやっと育児本番かと思いますので、張り切って頑張ります!

そうのすけ
20代男性 子供1人
1度目の育児休業は長男が1歳を過ぎた3月から4月にかけての1ヶ月間。子育て広場に通ったり、保育園の慣らし保育で呼び出されたりしているうちに、あっと言う間に終わってしまった。2度目の育児休業は次男が生まれてすぐの1ヶ月間。毎日オムツを何回も替えて、泣いたら抱っこで寝かしつけて、沐浴で体をきれいにしてあげた。この時も1ヶ月は、あっと言う間だった。
子どもたちの成長に伴い、保育園から小学校、学童保育に習い事と活動の範囲が広がり、それだけ覚える事や使う物、割くべき時間が増え、忙しい毎日。朝と夕方で担当を分け、朝は妻、夕方は私が保育園の送り迎えをし、夜は2人で家事育児をこなしていた。
そんな慌ただしい毎日に転機が訪れたのは昨年の7月、三男が産まれて、私と妻が同時に約10ヶ月間の育児休業を取ることにした。
これまでの2度の育児休業はどちらも1ヶ月と短く、正直その1ヶ月の前後は仕事も家庭も大忙しで大変だった。今回は上の2人の子の面倒も見ながら新しく生まれた三男の世話をしなくてはならず、会社や妻を説得して、なんとか妻だけでなく私も長期間休業することにした。現在、私と妻の両方が休みということで、家事育児は余裕を持って出来ている。午前と午後に分けて育児担当を決めることでお互いに自由になる時間も作れている。
職場復帰する4月まであと3ヶ月、三男はお座りが出来るようになり、離乳食も始まった。ハイハイやつかまり立ちをするようになると行動範囲な広がり、今以上に大変になりそうだ。育児休業を取って時間に余裕が出来たおかげで、小学生のドッヂボール大会の監督や保育園の豆まきの鬼役など、色々と依頼をされるようになった。保育園や小学校、地域の活動には父親に出来ることが沢山ある。ぜひ多くの父親が育児休業を取って、子どもたちとのイベントに参加して欲しいと思う。

高山 貴史
30代男性 子供3人
毎朝4時半に起き、妻子を起こさないよう家を出る・・・長男5才と次男2才のパパの1日の始まりです。始発で通勤し、フレックスタイムを朝型でフル活用。「〆切までに終わるか?明日、子供が熱出したら休めるか?」と自問しながら16:15まで働いた後、駅までダッシュ。2時間通勤の私のデッドライン超えを保育園の閉園は待ってくれません。
帰宅後、合流した妻が子供を入浴させる間に私が掃除。私が子供を着替えさせる間に妻が料理をし、園の出来事を聞きながら家族揃っての夕食。戦闘ごっこの悪役を楽しそうに務める妻を、皿を洗いながらみるのが食後の楽しみです。妻が寝かしつける間に入浴→洗濯→園の連絡ノートで一日が終わります。
日本人の家事・育児時間は1日平均で男性62分、女性299分だそうですが、我が家では帰宅後の4時間を妻とハーフ・ハーフでこのようにシェアしています。
このライフスタイルのきっかけは、長男の育休から妻が復職した直後。帰宅時間がばらつく私への「毎日計算できないのは戦力とは言わない」という妻の一言でした。戦力外通告に愕然としつつも、総合職としてのキャリアを出産で中断した妻の悔しさを正面から受け止めたいと思いました。
とはいえ、私の勤め先はゼネコン。仕事と子育ての両立が最も遅れている業界の1つ、建設業です。当然、毎日同じ時間に帰ることへの逆風も吹く。時間の使い方や仕事の優先順位付けに工夫し、周囲へも気を配りながらの綱渡りの日々です。
一方、最近は職場に女性が増えたこともありダイバーシティと銘打つ会が開かれ、コアメンバーとして参画するようにもなりました。後輩たちが「仕事か家庭か」の選択を迫られることなく「仕事も家庭も」を実現できる職場にすべく、育児経験を語り、将来彼らのイクボス・メンターとなるのが私の夢です。
こんな私へのご褒美でしょうか。今夏、三児の父になります。2度目の育休を取る私…熱い夏になりそうです。

りょうた
30代男性 子供2人
妻の出産の日からスタートして息子が1歳になるまでの1年間、育児休職を取りました。
自分も育児を経験し、いろんな意味で将来に備えようと考えたからです。
試練は育休の初日から起きました。出産は難産、帝王切開で産まれた息子は産まれてすぐに大きな病院に搬送。
妻と息子は離れ離れ、出産から数日間、搾乳した母乳を息子のところへ運び、僕が哺乳瓶で飲ませます。そんな状態からはじまりました。今考えても育休を取っておいて本当によかったと感じます。
そして妻も息子も順番に退院し、3人揃って家での生活が始まりました。
育休中は様々なセミナーに参加しました。それは父親業をするために必要なスキルを得るためです。内容は「家事育児」「新しい働き方」「ダイバーシティ」「ワークライフバランス」等々。有料の父親学級の講座も受講しました。
一方で、近所の自治体やボランティア主催の「赤ちゃんひろば」や「子育てひろば」、児童館の「赤ちゃんクラス」等々にも毎回参加しました。
ここでは50人近くいるママ達(女性)の中に男はいつも僕ひとりです。社会の現実を見ました。子育てに疲れているようなママも多かったです。
僕はできる限りママたちと話をしてパパの意識がどうすれば変わるかを男の立場として伝えてきました。パパを巻き込むためにパパ参加型のピクニックも開催し、ここでは思わぬパパ友もできて一石二鳥でした。
育休が終わり職場復帰後はセミナーで学んだ「定時退社」を実践し、毎日家族そろって夕食を食べ、息子と一緒にお風呂へ入り、団らんの時間を確保しています。
一番大変な時期の育児をひととおり経験し、柔軟な働き方も実践していますので、妻がいつでも再就職しても大丈夫な状態になっています。
そういう意味では育児は男を磨く「男の活躍の場」でもあるなと体験をもって感じました。

安藤紀彦
40代男性 子供1人
男性、女性に関係なく、仕事を続けながら、育児・家事がスムーズに両立できる社会になることが望ましいと考えています。
そのためには、男性が「育児休業」を取得することで、男性・女性に偏りなく育児・家事をする時間を各個人に提供し、企業・社会にもその認識をもってもらうことで、そのような社会が迅速に実現できる機会になると、11ヶ月の育児休業を取得中の者としては実感しております。
そして、その育児休業を、「欧州を中心に、企業が長期勤務者に対し1カ月~1年の長期休暇を付与する『サバティカル』制度」として個人が活用し、個人を成長させるきっかけとして、職場にとどまっているだけでは得られない経験をする機会と考えています。
そのため、育児休業の期間は、時間を見つけて、仕事復帰後の仕事と家庭とのスムーズな両立を見据えて、様々な研修会やイベントなどに参加し、講師や参加者とネットワークを構築しております。
そのような集まりに参加したことで、子育て世代だけでなく、介護の問題も含めれば、今後、全労働者の長時間労働をはじめとした働き方の見直しが必要だということを改めて考える機会になりました。
育児休業の期間中、息子の初めて覚えた言葉が「パパ」だったり、私が離乳食をあげているときに初めて「美味しい」と言ったりと、第1子の娘の時にはできなかった多くの「初めて」を共有できました。
また、第1子の娘とも保育園の送迎の際に、季節の移り変わりを一緒に感じる時間を共有でき、子どもが一緒にすごすことで、新たな出会いや経験をいっぱいさせてもらいました。
これからより多くの男性が「育児休業」を取得することで、育児・家事を通して、これまでの人生で体験しなかった学びと経験、新たな出会いの機会が増えると確信しています。
この育児休業という貴重な経験をさせてくれた、会社の方々、子供たち、妻に改めて感謝したいと思います。ありがとうございました。

ダイスケ
30代男性 子供2人