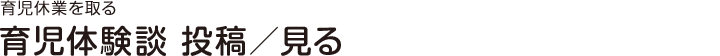見る
育児体験談を『見る』
入力欄に検索したいキーワードを入れて下の検索ボタンを押して下さい。
また、年代やエリア、お子様の人数などを選んで検索することもできます。
全 688件中、141件目 ~ 150件目を表示 (15/69ページ)
約一年間の育児休業を終えた。職場を離れると、何となく不安感、仕事が大好きって訳ではないつもりだったけど、依存ってあるののかも。現在保育所への迎えのため短時間勤務という形で復帰を果たしつつある。仕事も育児も大変。
・赤ん坊のパワーは凄い
世の中の赤ちゃん×ストレスでおこる事件、わからんでもない気がした。ミルクやオムツ、ダッコ、着替えなど通常できることをしても泣き止まない変なスイッチ入ると…うるさい!しつこい!わからない!
結構参る。自分の娘=可愛い(親バカ)じゃなかったら厳しいかも。せっかくだから泣き姿を動画にでも録っておこうか、と作業し始め、上手く録ることに集中しはじめると何気に焦りは消えた…そんな赤ちゃんのパワーに付き合う世のお母さん方は凄いなぁ、と思いつつ。
・大変?
ついつい考えるのが、仕事とどっちが大変か。結論はどっちも大変。そもそも競技の種目が違う。だから復帰後の方がトライアスロンじゃないけど仕事×育児×自分で大変。しかも家族みんなの力を借りまくる借物競走でもある!?
みんな頑張っているんですね~。早くこの新競技が楽しめる様になりたいものです。
・両親に感謝
こうして大変な思いをしてみると、自分がこんなコビトだった時は両親も大変だったんだろうな…いや、ここまで大変な子じゃなかったハズ(と思いたい)なんて感慨深く思いつつ、改めて感謝。借物競走への参加も感謝(笑)
・mont-bellザックはいい育児にいろいろ道具(グッズ)はつきものですが、一番使っているのは娘を背負うザック(リュックサック)、蒸れて暑くなりすぎないし、シェード(日除け)も付けられる。床に立つ(座らせたまま置ける)。荷物も結構入る、なかなかのスグレモノ。満帆はだんだん重くなり、気付けば10kg近くのダイエットに成功、スグレモノ(笑)

まぽとーちゃん
30代男性 子供3人
次男が産まれた時に長男と2人で過ごした1週間は改めてママの偉大さに気付きました…。仕事も大事だけど家庭の事も助けてあげなきゃ行けないなと痛感しました。

DIDDY3000
30代男性 子供2人
育休を2ヶ月間取得しました。
会社では第一号で、職場での反応は...辛い意見が多かったです。やはり年配の男性からはとくに...
ひどい人になるとなにかの宗教に入ったとか噂されたり...。
ただ
今考えるとその人に自分がきちんと説明出来てなかったように思います。
初めてのことは不安で辞めようかとも思った時期が
ありましたが娘のため妻のためそして次の世代のために取得しました。
いまでは育休を取ってよかったと思うし次の子供の時も取ろうと思います。
次はもっとレベルアップするぞー!!!
世の中の男性取得者がもっと増えますように。

ツキパパ
30代男性 子供1人
長女が誕生した時は育休を取った奥さんに頼りっきりでした。家のことは協力していたつもりだけど、やっぱり育児の主体は奥さん。保育園に通って子どもが発熱なんて時も奥さんに頼りっきり。二人とも仕事してるんだからこれじゃダメだよなと思いながらも仕事のことを考えるとなかなか・・・。次女を授かってからずーっとどうしようかもやもやしながらも出産予定日まであと4か月になった時、奥さんと話してみようと家族会議。「パパが1年間育休を取ったらうれしい?」と切り出すと奥さんは早く職場復帰したいけど言い出せなかったって。これはもう取るしかない!と一年間の取得を決意。上司に切り出すとやはりそこは会社もなかなか認めてはくれませんでした。なんで奥さんが1年じゃないの?って。それでも上司との話し合いを繰り返して、最後は「制度があるから」っていうことでなんとか押し切って申請。無事に第二子が誕生して1か月。仕事から完全に離れて育児に没頭。大好きな時間はお風呂上がりのベビーマッサージ。本当にいい顔してくれるんです。口をとんがらせたり、大きく開いたり、目をきょろきょろさせたり、見開いたり。一番触れ合えてるって思える瞬間ですね。長女とも遊ぶ時間が増えて毎日ゆっくりした時間を過ごせています。こうしてみると授乳以外は男でもできるんですよね。1か月検診が終わって、少し外にも出られるようになって毎日お散歩。最近は、結構パパがお子さん連れてる光景も見かけるようになってきました。これから、パパ友・ママ友ができたらいいなと思ってます。

いっちょ
30代男性 子供2人
うちは専業主婦ですが、子供のお風呂、歯磨き、お弁当の手伝い、朝食の準備などは毎日私がしています。
私の会社では専業主婦世帯は育休が取れないので育休はとっていません。共働きなら育休を取るのは父親として当然のことではないでしょうか?共働きで育休をとったからイクメン?笑わせます。じゃあ共働きですべてこなしている奥さんは?イクジョなんて言いますか?あたり前のことをして、さもイクメンぶってる人たちは、もっと父親としての自覚を持ってほしいです。やってあたり前なのです。なぜなら父親だから。
母親だけが育児や家事をするのが当然というわけではありません。父親もやって当たり前。イクメンのハードルが低すぎます。
少しやったくらいでイクメンなんて持ち上げるからロクな父親がいないのです。
このように思われないように、私は今日もイクメン目指して頑張ります。

ぽんぱぱ
30代男性 子供2人
7歳の娘と1歳の息子のパパです。
飲食店での勤務や「まちづくり」の分野での各行政とのタイアップ活動もあり、「休日」は、世の中のパパさんよりも少ないですが、出勤前の「朝時間」や帰宅後の「夜時間」を工夫して、子ども達とのコミュニケーションを図っています。
「朝時間」では、娘との小学校に登校するまでの支度を一緒にしています。洋服選び、ヘアセットなど、自分自身が「できる範囲」で接しています。また、小学校が自由登校ということもあり、一緒に登校してコミュニケーションを図ることもあります。
息子とは、抱っこ、ミルク、おむつ交換など、親として、普通のことではありますが、一般の方々と比べれば接する時間が少ない私にとっては、5分でも、「かけがえのない時間」です。
「夜時間」では、寝顔を見てから、娘の小学校や習い事で使う手提げ袋などの裁縫など、娘にはできない準備品の用意をして、いつも私のために用意してくれている「ラブレター」を読むのが日課です。また、1歳になったばかりの息子は、ミルクなどで、起きることがあるので、1日中、家事や育児で疲れている妻のかわりに面倒を見ています。
上記のように、「子ども達との時間を過ごす」ということは、親として当然なことであるが、
抱っこや手をつなぐなどのスキンシップ、父親としての立ち振る舞いも含めて、「ありのままの自分」を見てもらうこと、日々の生活こそが「子育て」だと考えています。
そして、何より重要視しているのは、妻への「感謝」です。2人の子どもを産んでくれた「妻」なくしての子育てはないので、妻への、女性への尊敬ができて、真の「育MEN」だと思っています。
「子どもは、親の背中を見て育つ」
親になって7年、その意味は、深く心に刻まれています。
今後も、当たり前のことを「当たり前」だと思わないで、その瞬間が「奇跡」だと思いながら子育てに取り組んでいきますので、よろしくお願いいたします。

宮脇 昇一郎
20代男性 子供2人
夫婦ともども仕事を転職してまだ右往左往するなか、子供を授かることになりました。妻は妊娠中も新しい職場で大きなお腹をかかえて仕事に励んでおり、子供が産まれたら、手伝わねば!と思っていましたが、いざ生まれてからは、手伝う!くらいの気合ではだめで、自分が育てる!くらいの気持ちがないとイクメンにはなれないことを痛感しました。
急な熱で仕事を休まねばならないことも多く、最初は「あー仕事ができない」と思っていましたが、子供が大病を患い入院生活を余儀なくされたとき、子供の傍らで看病しながら、一番大事なのは家族なのだと深く思い、人生の中で子育てをできるのは今しかなく、この時間を大事にしないといけないと教えられました。
今は、都会を離れて、自然豊かな田舎で、子供とアウトドアライフを楽しみながら、イクメン+仕事に励んでいます。
一度しかない人生、せっかくのイクメンになれたこの時間を満喫して楽しい人生を送れるよう、日々マイペースにやっております。

DEERさん
30代男性 子供1人
「パパの育児休業は特別なことじゃない。」
私たち看護職は、産後の女性は想像以上に心身共に疲労しており、パートナーの強力なサポートが必要であると考え、このように訴えてきました。
しかし、男性の育休取得率はわずか2%。残念ながら、私たちの声が社会に届いているとは言えません。
こうした現状を変えていかなければ――私自身もパパになって育休を取得し、改めてその必要性を実感したことが大きな転機となりました。父親の育休取得を当たり前と思われる社会に、看護職が先頭に立って変えていくべきだ。私は、大学病院で看護師として働く傍ら、パパの育児休業支援センターというNPO団体を設立し、活動をスタートさせることにしたのです。
平成25年6月には、「看護の心と技を織り込んだパパの子育てセミナーを開催するなど、男性の育児参加を推進することにより、産後うつの予防など妊娠・出産に関する心身の健康確保への支援に取組んでいる」と自治体からも評価され、大阪市健康増進計画「すこやか大阪21」のすこやかパートナーに登録をしていただきました。同時に、こうした活動は、新聞・雑誌などのメディアによって取り上げられ、社会的な注目を集めています。
男性なのに育休が必要?――しかし、時にはこんな反響をいただくことも。私は、その度に強く思うのです。「看護の声」を、もっともっと社会に届けていかなければ、と。
現在私は、行政などの依頼で父親の育児参加の必要性について講演をさせていただいたり、大阪市の男女共同参画審議会の委員を務めるなど、看護の声を発信する機会に恵まれつつあります。しかし、それでも社会を変えていくためには、まだまだ足りません。私たち看護職は、病院の中だけではなく、地域・社会のために力を発揮することが求められている。そう信じる看護職の仲間を一人でも増やして、活動の輪を広げていきたいと思っています。

古山陽一
30代男性 子供1人
来年度、1年間、医師である妻をサポートするため、育児休暇を取得します。

川原 広大
20代男性 子供1人
全てが、0からの出発で、悩むこと、イライラすることあります。
そして、ありました。
正直な所、、、、
人間ですからね。
やっぱり、ママにはかないません。(笑)
でも、僕にしか出来ないこと、
子供が、楽しい!!って思うこと
模索しながら、今まで、やってきました。
毎日のお弁当作り、掃除、洗濯、そして、子供と遊ぶこと、、、
気が遠くなることもあったし、投げ出したくなることもありました。。。
けど、子供の笑顔、僕に対する信頼感に救われながら、
大変な子育てを、何とかやっております。
今は、幼稚園のママ友に救われながら、楽しみながら、毎日を過ごしております。
ではでは、失礼いたします。

kazu
30代男性 子供1人