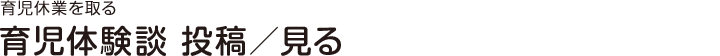見る
育児体験談を『見る』
入力欄に検索したいキーワードを入れて下の検索ボタンを押して下さい。
また、年代やエリア、お子様の人数などを選んで検索することもできます。
全 688件中、61件目 ~ 70件目を表示 (7/69ページ)
外資系企業で海外輸出入の貿易担当をしています。
半年前に双子の男の子が産まれ3児の父親となりました。
1年間の育児休暇を取得して現在6ヵ月があっという間に過ぎましたが、子供の細かい成長の一つ一つを間近で見れるという幸せを実感しています。
しかし今でも男性の育児休暇取得率は低く、世間からの理解は少ない感じです。
私は実の両親に育児休暇を取ると宣言したと同時に酷くパッシングを受け、
"なんでそんな物をとるんだ、収入や出世が無くなる、分かったもう勝手にしろ、お前は今日から無職だ!"
など、とにかく全てに対して否定的な意見を並べ相手にされませんでした。 その反面、妻の両親は、育児休暇に対して理解があり、週末は積極的に私達と子供達をサポートして頂けるので精神面でも大変助かっています。
その中で育児休暇を取得すると決断した理由は、私が妻の目線になって子育てについて考えたところ、4歳になる娘と双子を同時にサポート無しで一人で育てるにはあまりにも負担が大きく、なにより長女に全く構ってあげられないのが可哀想だと思ったからです。
娘は私の多少短気な性格と違い、とても優しく穏やかで、色々な事を我慢してしまいます。 妻が出産前に一か月ほど管理入院をして面会をした時もいつもニコニコ笑顔で身の回りのお手伝いを積極的にしたり、ママの似顔絵を描いてきて元気付けたり、双子の兄弟ちゃんが元気に動いているね!とエコーを一緒に見ながら楽しく会話をしてくれました。 帰る際も涙を目にたくさん溜めて必死に私の手を握り、病院の外へ出るまで泣くのを堪えていた姿が今でも印象的で家族の絆がどれだけ大事か改めて実感しました。
私は現在積極的に娘の幼稚園のイベントに楽しく参加しながら、日中は妻と一緒に双子と散歩に出かけ、毎日新しい発見を探す楽しみの中、過ごしています。

KENN
30代男性 子供3人
2歳の娘1人を持つパパです。
娘が保育園に通っていますが、妻の大変さがよくわかります。
私は平日仕事が忙しくて、ほとんど娘の面倒ができません。
土日の休日でできるだけ妻に休ませるようにサポートしています。
子供とのコミニケーションも大事なので、一緒に遊んだり、食事したり頑張っていますし、
その育児の間に楽しみも感じました。
これからも育児を継続頑張ります。

ネイキチ
30代男性 子供1人
「お母さんは凄い!偉大!!」
これが私の育休の感想であり、日々感じたことです。
我が家は、小学校教諭の妻と娘(4歳)と息子(1歳)の4人家族です。第二子の妊娠を機に、育休について考えるようになり、妻の育休終了・復職のタイミングで、2015年9月から7ヶ月間の育休を取得しました。
妻が出勤してからドタバタの1日が始まります。息子と一緒に娘を保育園に送り、そのまま児童館や買い物などの外出をして、帰宅後に昼食です。息子がお昼寝をしている間に、夕食の準備をして、夕方に娘を迎えに行きます。すぐにお風呂に入り、18時に妻の帰宅とともに家族揃って夕食です。子供を寝付かせた後に片付けや洗濯をして・・・あっという間に1日が終わります。
単純な生活のようですが、私にとって育児はストレス(食事に30分、寝付かせに1時間、夜泣き、常に一緒にいること等々)と孤独の戦いでした。育児ノイローゼや育児放棄する人の気持ちも分かり、日々「お母さんは凄い!」と痛感しました。
また、娘との関係では、保育園の行事や水泳教室に通い、お友達から羨ましがられ、自慢のパパになりました。家ではお風呂や読み聞かせなどで、ママよりパパ大好きっ子になりました!!
さらに、妻は子供の病気や降園時間を気にせずに存分に働き、人事評価で初めて特Aが取れ、今春に中心校へ栄転しました。一緒の時間が増えた一方、ケンカの日々を経て、夫婦仲がより深まりました。
そして、2016年2月、どこの認可保育園にも入園できず、育休を取った後悔や父親の役割を果たせなかったと思い悩み、絶望の1ヶ月を過ごしました。急遽、認可外保育園が決まった時、息子が「パパ、がんばったね。ありがとう♪」と微笑む姿に思わず涙が溢れました。この子の育児は始まったばかり、これからです!
最後になりますが、上司、同僚のおかげで、貴重な経験をすることが出来ました。感謝の思いを忘れず、これから仕事に貢献して参ります!

谷 正也
30代男性 子供2人
「育児によって自分の時間が奪われる。」ギター等の趣味が多い私にとって、育児に対するイメージはあまり良くありませんでした。しかし、実際に子供が産まれて時間を共にしていくと、可愛さからか「能動的」に子供に関わっていく自分に変化していきました。そんな中でも、仕事で疲れた休日等は育児に対して「受動的」な状態の時もあります。
そういう「受動的」な状態を「能動的」に変換する為に、二つの工夫をしています。まず一つ目は、「言葉のチョイス」です。例えば子供と二人で動物園に行くときは、「今日は二人でデートに行ってくるね!」と妻に言っています。「デート」という言葉を使うことにより、自分へのワクワク感を増幅させ、言葉の持っている力を最大限に利用しています。
二つ目は「育児ダイエット」です。30代後半になり、お腹の肉が気になりだした私は、育児とダイエットを何とかコラボできないかと考え、「育児ダイエット」を考案しました。子供を背中に乗せて腕立て伏せをやったり、浮かした足の上に子供を乗せ腹筋をやったりします。子供も私のお腹も喜び(鍛えられ)、この「育児ダイエット」のお陰で10キロの減量に成功しました。
会社では経理部に所属しています。部署的に「受動的」な仕事が多いのですが、子育てに対する「能動的」な姿勢が仕事にも影響し、自社の決算書への関心を高めることを目的として、社員向けの「決算書の読み方サイト」を立ち上げることができました。毎週記事を更新し続け、間もなく一年くらいになりますが閲覧者数も数千人おり、社内でも影響力のある情報サイトとなっています。
このように自分に変化を与えてもらった子供には感謝していますが、もう一つ感謝できることができました。今春にもう一人産まれます。五月出産予定ですが、経理の繁忙期の四月を避けて産まれてきてくれるあたり、どうやら最初の親孝行をしたいようです。

広中 秀俊
30代男性 子供1人
子供が産まれて、「幸せ」についてよく考えるようになりました。自分のやりたいことについて軸が出来たことで、今まで悩んでいた仕事や住まい、家族、プライベートなどの理想的なバランスイメージを持つことが出来ました。そのために家族と暮らすため移住することが自分にとって重要と考え、実行しようと計画中です。

林シンバ裕介
30代男性 子供1人
育休を取り、静岡の日本平へ行ってきました。妻の友人の結婚式が静岡の日本平ホテルであり、その付き添いです。15時から挙式が始まり、式が終わる20時まで、ずっと陽太と二人で過ごしました。完全母乳だったので、私にはご飯をあげられず最初は二人でどこまで一緒に居られるか不安でした。ドライブがてら清水エスパルスショップに行き、ベビー服を買い、それを着せてホテルのロビーや喫茶店に行きました。すれ違う時に「似合ってるね」「将来は選手として待ってるよ」「父子そっくりね」と言われ、二人で笑ってました。帰ってきた妻からは「陽太がエスパルス坊やになってる」と笑ってくれました。ここまで長く二人きりで過ごせたのは初めてだったので、絆が深まった気がします。

こしたろう
30代男性 子供1人
夕方16時半に会社を出て約1時間電車に揺られてた後、三男を保育園に迎えに行く。帰宅すると妻が夕食の準備を、子供達は宿題を始めている。我が家では子供達の宿題が終わらないと夕食は出てこない。
共働きの我が家の家事は基本的に私と妻で半分ずつ。たとえ片方が残業や出張で不在でも、全てのことを1人で出来るようにしている。
会社では、フレックス勤務を利用して朝は8時前に出社して夕方はほぼ毎日16時半頃に退社している。
3度目の育児休業から復職した後も、有給休暇を上手く使って保育園や小学校の行事などに積極的に参加している。平日の行事に参加すると未だにパパの参加率が低いことを実感する。確かにほとんどがママという平日イベントにパパは行きにくいだろう。私の場合、育児休業中からつどいの広場などでパパ友ママ友を作っていたこともあり、ママだけの場でも躊躇なく行ける。そして更に知り合いが増える。
この様に家事や子育ては、やればやるほど好循環を生むものだと思う。
子育てをする → 子が親を頼る → 子に親しみが湧く → やる気がでる
とは言え、一言で子育てと言っても、子供の数や性別、性格、年齢構成、自治体や会社の制度や環境など様々な要素でその大変さは全然違う。そこを上手くやるには、目標と役割をきちんと決めて、コミュニケーションを取り、PDCAを回すというマネジメントシステムの考えが有効だ。これで、だんだんと家事や子育てが上手くなり時間も短縮できる。おかげで我が家は3人の子育てをしながらも、私はオンライン英会話、妻はホットヨガと、自分の時間も楽しんでいる。
3人の子供を育てるのはお金もかかるし時間も取られるし大変な事だらけだ。しかし、上の子供達が末っ子の面倒をみて、楽しそうにしているのを見ると3人目がいて良かったと思う。
各家庭に子供が3人以上いないと日本の人口は増えない。ぜひ、多くの家庭が子沢山になることを願いたい。

たかぞう
40代男性 子供3人
もうすぐ2歳になる息子を持つ父親です。子供が産まれる前には想像もしていなかった生活を、今送っています。
子供が産まれる前は、育児に対して漠然と 「今まで通り仕事をして、残業のない日や休日に子供と触れ合えば良い」すなわち「協力」をすれば良いと考えていました。
その考えを一転させたのは、妻の言葉でした。「なぜ、私だけが主で育児を担わなきゃならないの?」
仕事で残業や出張は当たり前、育児は協力程度、そう思っていた私にとって、それは受け入れられない意見でした。もちろん妻も働いているので、協力するつもりはあったのですが、求められるレベルは「協力」でなく「積極的な参加」だったのです。
そうは言っても、妻も結局は私の考えを理解してくれるだろう、と期待していたのですが、その意に反して妻は周囲に「うちは旦那も育休取るから」などと、勝手に話を進めてました(笑)
今思えば、これが妻の作戦立ったのでしょうか? 段々と自分の考え方が固執していることに気付き、人生で大事なことは仕事以外にもある、同じ位育児も大事ではないか? と考えるようになりました。
妻の作戦に乗せられたのは間違いないですが、社会的な育休制度の充実、上司の後押しもあり、結果的に昨年4ヶ月間の育休取得を決断しました。
休業中は、息子と一緒に平日ランチに出かけたり、子育てサークルへ参加したりと 育児期間中ならではの経験をさせてもらいました。もちろん子育てサークルはママだらけ。行くのには、少しばかり勇気も要りました。
復職後も、フルタイム勤務の毎日ノー残業で息子の保育園の迎えに行っています。帰宅してから、御飯を作り、息子と一緒に食事、その後お風呂に入って、妻の帰宅が遅ければ翌日の保育園準備と寝かしつけまでします。
17時のチャイムが鳴った直後に退社すること、出張のやり繰りなど 大変な時もありますが、困難な状況に追い込まれてこそ、自分の実力が付くと思い奮闘中です。
もうすぐ第2子が産まれる予定です。
苦労も増えると思いますが、そんな状況も楽しみつつ、仕事と育児の両立を図っていきたいと思います。また、周囲の同じ境遇の人やこれからそうなるであろうという人達にも、自分自身の経験を伝えていって、男性の家庭参画を促していけたらと思っています。

ツヨパパ
30代男性 子供1人
昨年の4月、娘が2歳、息子が6ヶ月の時にパパママ育休プラス制度を活用して1年間の育児休業を妻と同時に取得しました。
私が育児休業を取得しようと決めたのは、妻の定年退職まで働き続けたいという思いを尊重しながら、自分のワークライフバランスも見直そうと思ったからです。
妻が第2子を妊娠した時から、時間外労働を減らして家族と過ごす時間を増やそうと意識しました。しかし、前年度から月平均50時間減らすことができたものの、まだ月平均90時間の時間外労働をしていました。意識しても過労死認定ライン以上に働いており、家事も全くやっておらず、休日は昼まで寝ているという状態でした。この状態では夫婦共働きで育児していくのは困難だと感じ、家事や育児能力を身につけるために夫婦同時育休を取得する決意をしました。
育休取得を決め、前年度の8月から管理職に相談し代替講師を探してもらいましたが、結局代替講師は見つかりませんでした。
最終的に担当の仕事内容を変えてもらい、その仕事の代替講師に来てもらい育児休業を取得させていただきました。
最初はママの代わりになれるようにと意気込んで、料理、食事介助、掃除、洗濯、公園遊び、風呂入れ、寝かしつけなど、ママの真似をしながら全てできるように頑張りました。妻の念願だった趣味の演劇出演も可能にして、私1人で2人の子どもを寝かしつけることもありました。
その過程で自分では頑張ってママの代わりなろうとしても、子どもはママが1番安心できる存在で、私はママの代わりにはなれないということがわかりました。娘は寝かしつけの時にママを探して泣き叫び、息子は1歳を過ぎるまで毎日私が散歩して寝かしつけていたのに、1歳過ぎからはママに寄り添ってしか寝なくなりました。
少し寂しく感じましたが、子どもにとって1番安心できる存在のママが安定して過ごせることが子どもにも大切だと思うようになりました。
そのために妻を支えていく意識をもつことがパパがやるべきことだと考えるようになりました。
仕事復帰しても自分にできることをやって家族を支えていこうと思います。
自分の限界を知り、夫婦共働き育児のヒントを得られ、同時育休を取得して良かったです。

日高純一
30代男性 子供2人
私は2015年度1年間育児休業を取りました。働いているのが妻、家にいるのが私と3歳と1歳の男の子いう生活を選びました。育児休業を取った理由は二つあります。
1つ目は妻の子育てストレスを何とかしてあげたいと思ったからです。ある日の夕方、仕事中の私の携帯、に妻から電話がありました。電話を出ると騒ぐ子供たちの声と泣きながら「今日は早く帰ってこられるの?」という妻の声をききました。子育てを妻に押し付けていないか?自問自答するきっかけとなりました。
2つ目は私が高校教員をしていることです。自らの経験がこれからの指導に生きると思ったからです。こういう生き方もあるし、自分の経験や考えたことをこれから父や母になる生徒たちに伝えられないか、と思ったからです。
育児休業を取得して実感したことの一つに「自分は自分の住んでいる地元を何一つ知らない」ということに強く気付かされました。歩道に死角を作らないように草刈りをするおじいさん。公園の空いた花壇に苗を植えて花を育てるおばあさん。いままで見えてこなかった善意を肌で感じ、時には一緒に手伝いもしました。
また、地域活動やワークショップを主催する高校の同級生から誘ってもらい、参加することもありました。その中で知り合った人たちは自分の地元を愛し、お金でない豊かさを持った生き方を知りました。育児休業をとって子どもと歩みがゆっくりになって今まで見えなかったものが見えました。私の中で大きな発見でした。
先日、高校で英語を教える妻の「男女の性差」について考える授業のなかで、男の育児休業の取得者として授業に参加させてもらいました。授業を受けた生徒たちは感想を書いたプリントに「男性の家事や育児の参加の重要性がわかった」、「これまでの常識にとらわれない新しい生き方を感じる事ができた。自分もやってみたい」、「カッコいい」「結婚したくなった」といった感想をいっぱい書いてもらえました。この授業を受けた生徒たちの意識が少しでも変わったら嬉しいなと思った出来事でした。
あと2ヶ月の主夫生活。まだまだ新しい発見や出会いを子どもたちと一緒にできればいいな、と日々思っています。

柳田 一匡
30代男性 子供2人